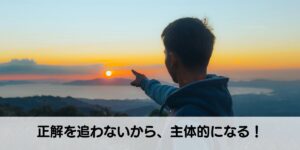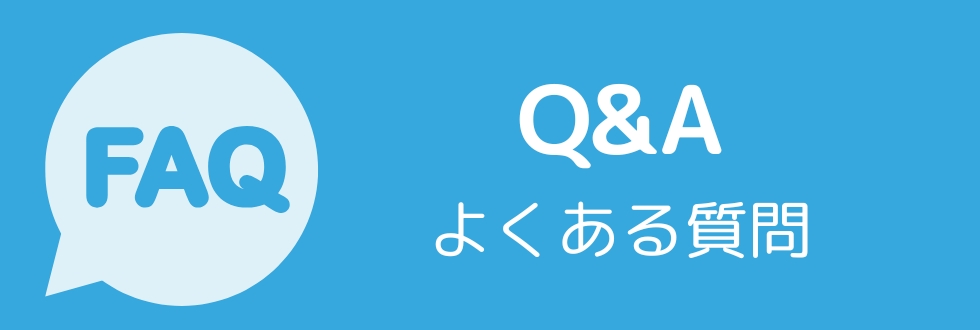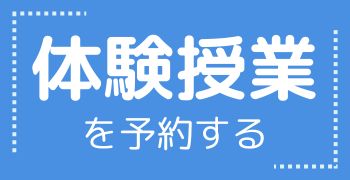
探究心・好奇心の礎

「めんどうくさい」の裏側にあるもの
前回の記事では、「失敗を恐れないチャレンジャーを育てる」ための心構えについてお話ししました。今回は、もう一つ子どもたちと向き合う中で気になっている言葉、「めんどうくさい」について考えてみたいと思います。
ロボット制作やプログラミングといった、子どもたちが本来ワクワクするはずの活動の中でも、「こうしてみたら?」「どうしてこうなるんだろう?」と声をかけると、「めんどうくさい」と返ってくることがあります。あんなに夢中だったのに、なぜ?
もちろん、単なる口癖になっていることもありますし、「毎回同じことをやるのが面倒」「考えるのが苦手」「今はやりたくない」など、背景はさまざまです。ただ、この「めんどうくさい」に好奇心が負けてしまっているとしたら、それは少し心配な兆候です。
学びの出発点は「なんで?」「どうして?」
「なんでこうなるの?」「えっ、すごい!」——そんな驚きや不思議に思う気持ちが、学びの出発点になります。つまり、好奇心や探究心です。
たとえばレゴで作る動くモデルは、クレーンやエレベーター、公園の遊具など、すべて私たちの身近にあるものが題材です。普段見慣れているからこそ意識しにくいものですが、改めてじっくり見てみると、「どうやって動いているんだろう?」と疑問が湧いてきます。
「身近なこと」に気づける感度が好奇心を育てる
私自身、子どもの頃から動くものに強い興味がありました。家電を分解しては組み立てられなくなり、親に叱られることもしばしば。けれど、その「なんで?」「どうなってるの?」という気持ちが、ずっと好奇心の源泉でした。
好奇心の礎は、特別な体験ではなく、実は「身近なちょっとしたこと」に気づけるかどうかにあります。たとえば、小さな子どもが公園に向かう途中で、何度も立ち止まってしまうあの寄り道。大人には「無駄」と思える時間も、子どもにとっては発見の宝庫なのです。
ところが最近では、子どもたちも忙しく、じっくり観察したり、自分で考えたりする時間が不足しがちです。だからこそ、私たち大人が「好奇心のアンテナを立てる」機会を意識的につくってあげる必要があるのかもしれません。
まとめ:探究心は「ちょっとしたこと」に宿る
子どもの「めんどうくさい」という言葉の裏にある本心を見極めながら、身近なことに気づける感性——これこそが探究心・好奇心の土台です。難しい教材や刺激的な体験ではなく、「目の前のあたりまえ」に目を向けること。それが、未来の学びを大きく育てる第一歩になります。