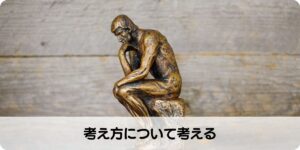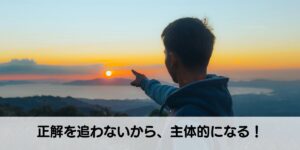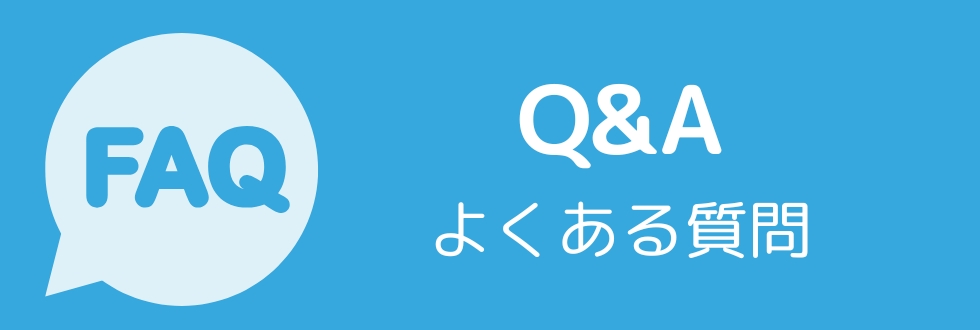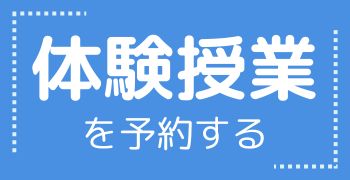
考え方について考える
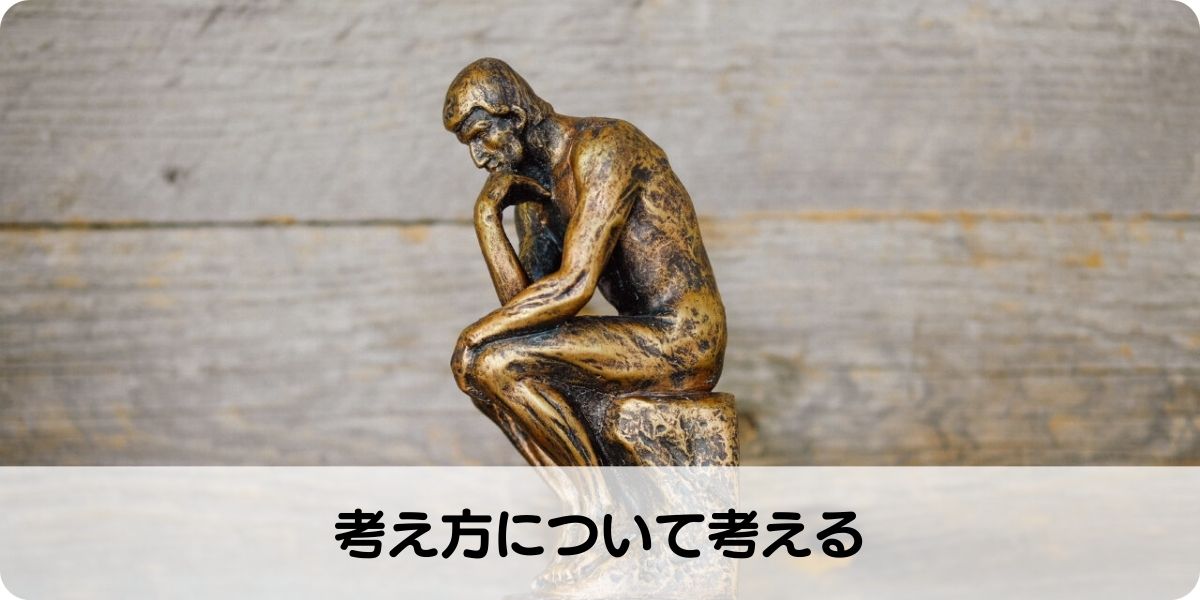
ロボット(ハードウェア)を制作しているときになぜか思っていたような動きにならない、プログラミングをしていてロボットが違った動きをする、しかも原因が分からない。
まだまだ経験が少なく考えることを学んでいる成長過程の子どもたちにとっては、心が折れてしまいかねない一大事です。
こんな時、どのように考え、問題を解決すればよいのでしょうか。
ロボットがうまく動かないとき、どう考える?
ロボット制作やプログラミングをしていると、「あれ?思った通りに動かない」「なぜか原因が分からない」といった壁にぶつかることがあります。これは、小学生から中学生・高校生に進むにつれて、誰もが経験する“学びの中のつまずき”です。
特に中高生の生徒にとっては、思い通りにいかない経験が「自分には向いていないのかも」と自信を失うきっかけになることも。でも、実はここが“考える力”を育てる絶好のチャンスなのです。
問題解決力を育てる「考え方」って?
私たちロボット教室テディスでは、「子どもたちが自分で考え、判断し、行動できるようになること」を教育の目的としています。では、どんなサポートや環境がその力を育むのでしょうか?
そんな問いにヒントを与えてくれたのが、人工知能研究のパイオニアであるマーヴィン・ミンスキー博士の著書『創造する心〜これからの教育に必要なこと』です。
この本には、子どもたちが問題にぶつかった時にどう考えればいいのか、具体的な思考のパターンが紹介されています。
MIT流!問題解決のための9つの思考アプローチ
書籍の中で紹介されている問題解決のプロセスは以下の通りです。
- 問題に見覚えがあるなら…
- それでも難しいなら…
- 見覚えがなければ…
- アイデアが出過ぎるときは…
- 内省(自分の思考を見直す)
- なりきり(誰かになりきって考えてみる)
- 一時退避(いったん手を止める)
- 解法の当てはめ
- それでもダメなら…誰かに助けを求める!
特に注目したいのが⑤~⑦のアプローチ。
「休む」「なりきる」「振り返る」も立派な戦略
「内省」「なりきり」「一時退避」——この3つは、行き詰まったときにこそ試してほしい考え方です。
たとえば、一時的に問題から離れることで、視野が広がり、違う角度からのアイデアが生まれることがあります。実際、私もよく“お風呂でリセット”をして、ひらめきを得た経験があります。
最後に:答えを教えるのではなく、支える
そして最後のステップ、「誰かに助けを求める」。これはとても大切な行動です。私たち大人や講師は、子どもたちが自ら考え抜く力を失わないよう、見守り、必要な時にだけそっと手を差し伸べる存在でありたいと考えています。
「すぐに答えを教えず、考える時間を尊重する」。テディスでは、こうした姿勢を通じて問題解決力や自己効力感を育てていきます。
- 小学生〜高校生が在籍し、段階的に考える力を育成
- 「問題解決力」「探究力」を重視したカリキュラム
- ロボットを通じて、失敗から学ぶ経験ができる
「考え方について考える」。そんな視点で学びたい中学生・高校生の皆さん、ぜひテディスのロボット・サイエンスコースを体験してみませんか?