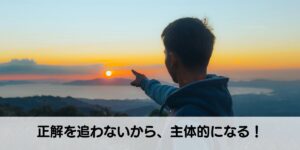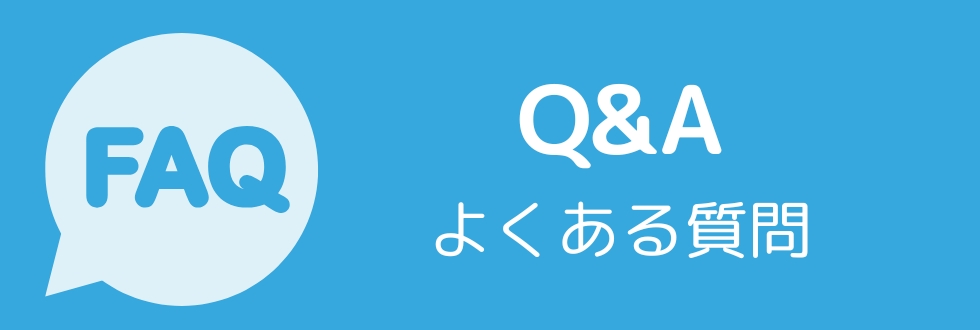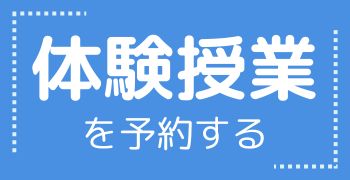
「21世紀型スキル」とは?

「考える力」「やり抜く力」「他者と協力する力」——これらは、これからの時代を生き抜くために欠かせない力です。情報技術がますます進化し、答えのある問題より“正解のない課題”に向き合う場面が増えています。学校のテストだけでは測れない、そんな力をどう育てるかが、いま保護者の間でも注目されています。
この記事では、「21世紀型スキル」と呼ばれるこれからの社会に必要な力と、その育て方、そして私たちテディスが実践している取り組みについてご紹介します。
21世紀型スキルとは?その必要性と背景
なぜ今、「知識」より「活用力」が求められているのか
今の社会は、情報があふれ、変化が激しく、価値観も多様です。かつてのように「決められたことを、正確にこなす」ことだけでは、対応できない時代です。
これからの子どもたちには、「自ら課題を見つけ」「仲間と協力しながら」「自分で答えをつくり出す」力が求められています。
学校教育の中でも「アクティブラーニング」や「探究型学習」といった言葉が注目されるようになりましたが、まだまだテストの点数や受験が中心という現状もあります。
ATC21sによる21世紀型スキルの定義
世界的に教育の未来を考える団体「ATC21s(21世紀型スキルの評価と指導)」は、次のようにスキルを分類しています。
◎ 思考の方法(Ways of Thinking)
- 創造力とイノベーション
- 批判的思考、問題解決、意思決定
- メタ認知(学びの学習)
◎ 仕事の方法(Ways of Working)
- コミュニケーション
- コラボレーション(チームワーク)
◎ 仕事のツール(Tools for Working)
- 情報リテラシー
- ICTリテラシー(情報通信技術に関する理解)
◎ 社会生活のスキル(Living in the World)
- 地域・国際社会での市民性
- キャリア設計、人生設計
- 社会的責任、文化的理解
これらはまさに、これからの社会を生きる子どもたちに欠かせない力です。
未来のために育てたい3つの力
①「考える力」…試行錯誤しながら答えを導く
ロボットを思い通りに動かすには、何度も試して、うまくいかない原因を探る力が必要です。この“試行錯誤のプロセス”こそが、「考える力」の土台になります。
②「やり抜く力」…あきらめずに工夫し続ける
トラブルや失敗はつきもの。でも、そこから立ち上がってまた挑戦する。この経験の積み重ねが「やり抜く力」を育てます。
③「協働する力」…人と協力して課題に挑む
友だちと一緒に作業をしたり、アイデアを出し合ったりする中で、自然と「伝える力」「聞く力」「チームで働く力」が育まれます。
テディスの授業で実践していること
「試行錯誤する学び」をどう実現しているか
テディスでは、ロボット制作やプログラミングを通じて、子どもたちが「やってみる → 失敗する → 改善する」のサイクルを自然と体験できるように設計された授業を行っています。
協働・コミュニケーション力を育てる場面とは?
低学年のうちから「グループで課題に取り組む」活動を取り入れています。先生が一方的に教えるのではなく、子ども同士で学び合う場面を大切にしています。
子どもたちが自然と「21世紀型スキル」を使い始める瞬間
私たちが見ていて、最も感動する瞬間の一つが、「子どもが自ら気づき、自分の言葉で解決方法を話し始める」場面です。これは、「学び方を学んでいる」証拠でもあります。
まとめ:正解よりも、「学び方」を育てよう
社会の変化に対応できる子どもを育てるには、「今の社会で役立つ力」だけでなく、「これからの社会をつくる力」を育てる視点が必要です。
テディスでは、知識を教え込むのではなく、「学び方を学ぶ」ことを大切にしています。21世紀型スキルを育てるために、ロボット制作やプログラミングは、とても有効な学びの手段です。
子どもたちが未来を切り拓いていくために、今、どんな環境を与えるか。一緒に考えていきましょう。