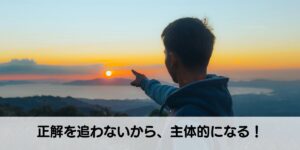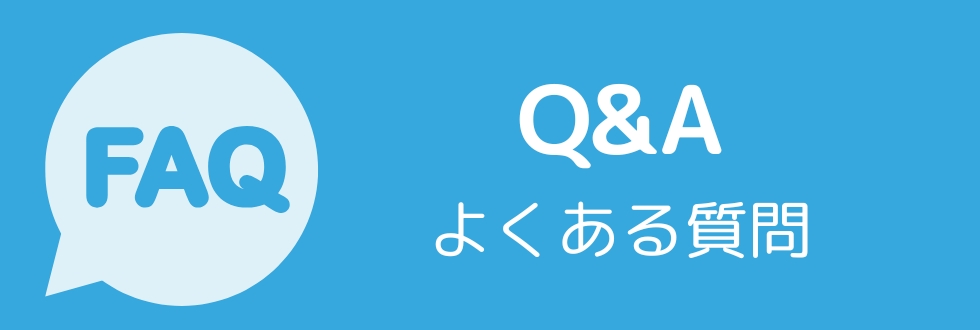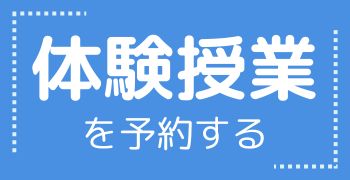
中学入試でもプログラミング?

プログラミングが中学入試の科目に?
近年のプログラミング教育の進展により、中学入試にプログラミングを取り入れる学校が増え始めています。
2020年4月には小学校でのプログラミング教育が必修化され、2021年からは中学校、そして2022年には高等学校でも必修となることが決まっています。さらに、2025年の大学入学共通テストでは「情報(プログラミングを含む)」が教科として導入予定となっており、受験環境にも大きな変化が起きつつあります。
中学入試でプログラミングを採用している学校
すでに、中学入試にプログラミングを導入している私立中学校が存在します。以下はその一例です:
- 駒込中学校
- 聖徳学園中学校
- 大妻嵐山中学校
- 相模女子大学中学部
プログラミングの問題といっても、単にコードを書くのではなく、「プログラミング的思考を問う問題」や「プレゼンテーション」「ディスカッション」といった、表現や思考力を評価する形式も見られます。
大学入試における教科「情報」について
高校における情報科目は、新学習指導要領により次の2つに分かれます。
情報Ⅰ(共通必履修)
- プログラミングを含む基礎的な内容
- 自分の目的に合った情報ツールを選び、活用・表現できる力を育てる
情報Ⅱ(選択科目)
- より発展的な内容
- システム全体を設計・構築・運用できる力を養成
この科目では以下のようなテーマが扱われます。
- 情報社会の問題解決
- コミュニケーションと情報デザイン
- コンピュータとプログラミング
- 情報通信ネットワークとデータ活用
「なんだか難しそう…」と思うかもしれませんが、小さい頃から自然に触れておけば、将来も抵抗感なく学んでいけるはずです。
個人的な視点から
プログラミングの重要性が急激に高まっている一方で、地域や学校によって対応の差が大きいと感じます。
私はもともと「テスト対策」というものに少し抵抗があります。もちろん、テスト前に復習することは大事だと思いますが、「点を取るためのテクニック」ばかりが優先され、内容の理解が置き去りにされることがよくあるからです。
たとえば算数で「分数の割り算はひっくり返してかける」と覚えていても、「なぜそうするのか」を説明できる人は意外と少ないですよね。意味を理解して考える学びこそ、後の思考力につながるはずです。
プログラミング教育も、「英語教育と同じように、理想は素晴らしいけれど現実が伴わない」とならないよう、本来の目的を見失わずに取り組んでほしいと願っています。